生後0ヶ月(新生児期)は昼も夜も関係なく赤ちゃんが寝たり起きたりして、ママパパはお世話がとっても大変な時期ですよね。
生まれたての赤ちゃんが可愛いくて、ずっと抱っこしながらトントンしたりゆらゆら揺れたり、頑張りすぎていないでしょうか?
寝かしつけを長時間続けても赤ちゃんが全然寝てくれないと「やばい、しんどい、休みたい、自分の時間が欲しい」ってストレスを感じてしまうようになってきます。
この記事では、生後0ヶ月から使えるスヤスヤ眠るための知識、ノウハウをお伝えします!もちろん生後0ヶ月以降も使えるものばかりなので、ここで得た知識をぜひ活用してみてください。

寝かしつけのつらさを克服するため、赤ちゃんの寝かしつけに関する本をたくさん読んだので、実験データや科学的根拠のある信頼できる情報を元に記事を作りました。
実は赤ちゃんの睡眠は前頭前野の発達に影響しており、極度の睡眠不足は、情緒発達の問題や問題行動が1.5〜3倍に増加しているという研究結果もあります。適切な睡眠時間(目安)も説明しますので参考にしてください。
この記事を読むことで、赤ちゃんがスヤスヤ眠るための正しい知識・ノウハウを身につけて、赤ちゃんを健康に育てるとともに、ママパパは自分の時間を増やしましょう。
ママパパも心と体に余裕をつくって、今以上に幸せな気持ちで赤ちゃんとの時間を過ごせることを願っています!
まずは、生後0ヶ月のおねんねの結論です。
- 眠りやすい環境を整えよう
- 夜は真っ暗にして、体内時計を整えよう
- 夜はホワイトノイズを使ってほどほどに静かにする
- 温度湿度は大人が快適(少し涼しいくらい)に調整する
- 赤ちゃんの不快を取り除こう
- 赤ちゃんが起き続けられる時間は約40分なので、積極的に寝かしつけをしよう
- お昼寝しすぎている場合は、お昼寝時間を減らして夜の睡眠を増やそう
- 赤ちゃん自身に不快な要素がある場合は、原因を対処しよう
- 寝かしつけテクニックを知ろう
- 5つのスイッチを使って穏やかな気持ちにして入眠させよう
- 寝かしつけた状態をキープするために、簡単な寝かしつけか起こして寝かそう
時間が足りないというかたは、大きくなってからも睡眠習慣に必ず役立つ「体内時計を整える」だけでも読んでいただけると嬉しいです。
眠りやすい環境を整えよう
生後0ヶ月の赤ちゃんがスヤスヤ眠るためには、眠りやすい環境が整っていることが大切です。ではどのような環境が良質な睡眠を得るために必要なのでしょうか?
赤ちゃんがぐっすり眠るポイントをまとめると以下になります。
- 体内時計を整える(昼は明るく、夜は真っ暗)
- ほどほどに静かする
- 温度湿度を調整する(温度:20〜22度、湿度:40〜60%)
体内時計を整える(昼は明るく、夜は真っ暗)
生後0ヶ月は体内時計がでたらめで昼も夜も関係なく眠ります。生後2ヶ月ごろから昼夜の区別がつくようになると言われています。それならなぜ生後0ヶ月から、昼は明るく夜は真っ暗にする必要があるのでしょうか。
実はエール大学の実験によって、生まれた瞬間から光をコントロールしてあげることで夜にスヤスヤ眠るようになることがわかっています。
予定日より早く生まれ、NICU(新生児集中治療室)に入っている赤ちゃんたちの、あるグループには一定の明るさの弱いライト、あるグループには昼と夜で明るさの変わるライトを当てる、という実験がエール大学でおこなわれました。すると、明/暗のサイクルで育てた赤ちゃんのほうが、日常生活のリズムが早く発達し、昼はより活発に、夜はよく眠るようになったのです。
赤ちゃん寝かしつけの新常識(著者:ソフィア・アクセルロッド)P56-57

この知識を知ってから、生後0ヶ月から朝の決まった時刻に太陽の光を15分は当てるように意識して、赤ちゃんが体内時計を整えるサポートをしています!
人の体は体内時計のリズムに合わせて朝には朝には消化吸収がよくなり、夜には眠たくなるようにできています。つまり、体内時計が整えば夜には眠たくなるということになります。
体内時計を整えるのも体内時計を乱すのも、最も影響力が大きいのが光です。眠っている時間に光を浴びることで体内時計がリセットされることがわかっていますので、夜にはできるだけ光を浴びないための工夫が必要です。
- 部屋の外側からの光を遮断
- 雨戸を閉める
- 窓を遮光する
- 部屋の内側からの光を遮断
- テレビやスマホをつけない
- 天井の常夜灯は消す
- スイッチ類の灯りを隠す
特に避けたい光は、体内時計に最も影響を及ぼす波長の短い青い光(ブルーライト)です。
赤ちゃんの就寝時間に向けて、部屋は暖色系の間接照明にしたり、テレビやスマホの使用を控えると影響を小さくすることができます。スマホであれば、Night Shift(iOS)機能やブルーライトカットフィルムを使用するというのも一つの手です。
ただ、生後0ヶ月だと、夜中に赤ちゃんの授乳やミルク、おむつ替えなどの作業をするためにどうしても深夜にも明かりが必要になります。
体内時計に最も影響を及ぼすのは青い光ですので、波長の長い赤色のナイトライトを夜の間中つけておいて作業を行うと赤ちゃんの体内時計を乱さずに赤ちゃんの様子を確認できます。ちなみに、青と赤の中間色(例えばスイッチなどの緑色の光)にも青色の光の成分が含まれています。
赤い光は、メラトニン (睡眠をうながすホルモン)濃度に影響しないので、寝ている赤ちゃんのじゃまをしません
赤ちゃん寝かしつけの新常識(著者:ソフィア・アクセルロッド)P61

大半の書籍が体内時計(生活リズム)を整えることの大切さを伝えていたので、おむつ替えなどで夜間に体内時計を狂わせないためにも、ネットで調べて赤色が出せるナイトライト(Amazonで安めのやつ)を買いました。
ほどほどに静かにする
結論から言うとホワイトノイズ(シャーシャーした音)を流すことで、寝かしつけに効果があることが知られています。
ロンドンの科学者たちが、生後2〜7日の新生児にホワイトノイズを聞かせたところ、80%が5分以内に眠りに落ちたのに対し、ホワイトノイズを聞かせていない新生児の場合は、5分で眠ったのは20%だけだったと発表しました。
赤ちゃん寝かしつけの新常識(著者:ソフィア・アクセルロッド)P80
周囲の生活音を聞こえにくくさせるだけでなく、それ自体にも赤ちゃんを落ち着かせる効果があると言われています。また、寝た時と夜中に起きた時の環境が異なると不安になるため、ホワイトノイズは寝ている間中、ずっと流し続ける方が良いと言われています。
自然に聞く音ではないので、聴覚への影響が気になるところですが、音量を小さくすれば問題ありません。「スタンフォード式 最高の睡眠」の著者としても知られる西野精治さんも以下のように述べています。
ここでいう音は50〜60デシベルで静かな事務所にいる程度の大きさ。聴覚への影響は心配ありません。一般的には90デシベル以上の音を聞き続けると難聴になる可能性があると言われています。
ママと赤ちゃんのぐっすり本(著者:愛波文 監修:西野精治) P84
ちなみにホワイトノイズは換気扇の音でも代用できるそうなので、換気扇を回しつづけるというのも簡単に試す方法の一つです。

ホワイトノイズは、アプリやYoutube動画で調べたら色々見つかります。
聴覚への影響はなく、スヤスヤ眠れる赤ちゃんの方が多いようなので、音量を小さくして、音源の位置(2mほど)を離した上で使ってみようと思います。
※24時間換気で代用していますが、うちの子にはあまり効果がないのかしら・・・
温度湿度を調整する(温度:20〜22度、湿度:40〜60%)
赤ちゃんも大人も快適に過ごせる環境が必要です。それの目安が温度20〜22度、湿度40%〜60%と言われています。夏や冬や地域によって快適な室温は変化しますので、エアコンや加湿器を活用して快適な室内環境を作り上げるのがおすすめです。
目安の温度20〜22度では少し寒いように感じますが、赤ちゃんの方が大人よりも涼しい方が適温と言われています。
乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクを下げるうえでも、暑すぎないことは重要なこと。乳児の体温が高くなりすぎないよう、大人が薄着で快適だと感じる温度に部屋を保ち、過度に服を着せたり、温めすぎないことを推奨しています。
マと赤ちゃんのぐっすり本(著者:愛波文 監修:西野精治) P46
もちろん赤ちゃんごとの個人差がありますので、赤ちゃんの様子をよく観察して、暑すぎて背中などが汗ばんでいないか、逆に寒すぎて手足が冷え切っていないか、顔色が悪くなっていないかなどを確認して調整してください。

大人は少し肌寒く、赤ちゃんが肌着とおむつだけで過ごせるぐらいの室内環境が理想なのかもしれません。
赤ちゃんの不快を取り除こう
赤ちゃんの不快にはどんなことがあるでしょうか。ここでは以下について説明します。
- 睡眠時間が適切な量ではない
- 赤ちゃん自身に不快な要素がある
睡眠時間が適切な量ではない
生後0ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間についてまとめると以下になります。それぞれ細かく説明します。
- 赤ちゃんが起き続けられる時間(約40分)を意識しよう
- お昼寝の時間をコントロールして、夜に眠れるようにしよう
赤ちゃんが起き続けられる時間は約40分
赤ちゃんは睡眠時間が足りていないと眠れないことがストレスになって、更に寝つきが悪くなって激しく泣き叫ぶことがあります。赤ちゃんの適切な睡眠時間はそもそもどれぐらいなのでしょうか?
WHOのガイドラインによると、0ヶ月~3ヶ月までに必要な睡眠時間は14~17時間。ガイドラインとも一致している、赤ちゃんの活動時間(=起き続けられる時間)をわかりやすくまとめた表を以下に示します。
| 月齢 | 活動時間の目安 | ベストな睡眠時間(合計) |
| 0〜1ヶ月 | 〜約40分 | 約14〜17時間 |
| 1〜2ヶ月 | 約40分〜1時間 | 約14〜17時間 |
| 2〜3ヶ月 | 約1時間〜1時間20分 | 約14〜17時間 |
| 4〜5ヶ月 | 約1時間20分〜1時間30分 | 約12〜15時間 |
| 6〜8ヶ月 | 約2時間〜2時間30分 | 約12〜15時間 |
| 9ヶ月 | 約2時間30分〜3時間 | 約12〜15時間 |
| 10〜1歳2ヶ月 | 約3時間30分〜4時間 | 約12〜15時間 |
| 1歳3ヶ月〜1歳半 | 約4時間〜6時間 | 約12〜15時間 |
| 1歳半〜3歳 | 約6時間 | 約11〜14時間 |
| 4歳〜5歳 | 約5時間〜12時間 | 約10〜13時間 |
表を見るとわかるように生後0ヶ月の赤ちゃんが起き続けられる時間はたったの40分です。
赤ちゃんが目を覚ましている時に、おむつを替えたり、授乳やミルクを与えたり、沐浴していると、あっという間に眠くなる時間がやってきます。

赤ちゃんによって起き続けられる時間は違うものの、赤ちゃんがあくびをしたり眠そうな仕草をする前に、ママパパがタイミングを見計らって積極的に寝かしつけてあげるといいんだね!
お昼寝しすぎている
お昼寝をしすぎて夜に眠れないと言うパターンもあります。昼と夜の合計睡眠時間が十分取れている場合は、睡眠圧が減ってしまい眠たくならないという状態に陥ります。
大人でもお昼寝しすぎたら夜にあまり眠たくならないのと同じですね。
夜の睡眠時間とお昼寝の時間配分について18カ国のこども6万9544人のデータをわかりやすくまとめた表を以下に示します。
| 月齢 | 夜の睡眠時間 | お昼寝の時間 | 合計睡眠時間(お昼寝回数) |
| 1週 | 8時間 | 8時間 | 16時間(4回) |
| 1ヶ月 | 9時間 | 6時間 | 15時間(3回) |
| 3ヶ月 | 10時間 | 3時間30分 | 13時間30分(3回) |
| 6ヶ月 | 10時間30分 | 2時間30分 | 13時間(2回) |
| 9ヶ月 | 11時間 | 2時間 | 13時間(2回) |
| 12ヶ月 | 11時間 | 1時間30分 | 12時間30分(2回) |
| 18ヶ月 | 11時間30分 | 1時間 | 12時間30分(1回) |
| 2歳 | 11時間 | 1時間 | 12時間(1回) |
| 3歳 | 10時間30分 | 30分 | 11時間(1回) |
| 4歳 | 10時間30分 | なし | 10時間30分 |
| 5歳 | 10時間 | なし | 10時間 |
| 6歳 | 9.5時間 | なし | 9.5時間 |
この表によれば、月齢が1週のケースでは授乳orミルクを3時間に1回と想定すると、1日で8回の授乳orミルクを行い、その都度2時間の睡眠をとるというペースになります。
一方、月齢が1ヶ月のケースになると、月齢1週の頃よりもお昼寝の時間が2時間減ります。月齢1週のケースと同じくお昼寝を8時間すると、月齢1ヶ月の赤ちゃんは夜の睡眠時間は7時間で十分ということになります。
つまり月齢1ヶ月になると、20時に寝かしつけたら朝の3〜4時ぐらいに目が覚めても、赤ちゃんにとっては十分寝ているということになります。ママパパにとっては「夜に全然眠ってくれない!」と感じるかもしれませんね。

夜にスヤスヤ眠って欲しい時は、お昼寝の時間をコントロールしてあげると良いね!
赤ちゃん自身に不快な要素がある
赤ちゃんがスヤスヤ眠るためには、赤ちゃんがご機嫌でいることが大切です。赤ちゃんのママパパが一番わかっていると思うので、ありがちな項目と解決案をざっと列挙します。
- お腹が空いている
- 胃に空気が溜まっている
- オムツが気持ち悪い
- 便秘になっている
- 鼻が詰まっている
- かゆい
- 適時適量の授乳やミルクで満足させる
- ゲップをさせる
- オムツ交換をおこなう
- 「の」の字マッサージをおこなう
- 部屋をきれいにして埃を減らしたり、鼻吸い器で鼻水をとる
- 保湿する
他にも数えられないぐらい色々な要素があると思いますが、全部対応しても泣き止まないことがあります。そんな時はただ泣きたいだけで、決してママパパのせいではありません。
生後2週間くらいから始まり、生後2ヶ月くらいをピークに生後5ヶ月くらいまでどうんいもならないほど泣くことがあると言われています。この現象を頭文字を取って「Purple Crying」と呼びます。
すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本(著者:ねんねママ(和氣春花))p21
P:Peak of crying 生後2ヶ月がピーク
U:Unexpected 泣く理由が予想できない
R:Resists soothing なだめることもできない
P:Pain-like face 痛くなくても痛そうに泣く
L:Long lasting 長く、1日5時間以上泣くこともある
E:Evening 特に、午後から夕方によく泣く

どんなに頑張ってても赤ちゃんが泣き止まない時は、「たそがれ泣き(Purple Crying)なんだ!」と自分に言い聞かせることで、気が楽になってもらえれば嬉しいです。
寝かしつけテクニックを知ろう
寝かしつけのテクニックをまとめると以下の2つになります。それぞれ説明していきます。
- 穏やかな気持ちにさせて入眠させよう
- 眠っている途中で目を覚ましにくくさせよう
穏やかな気持ちにさせて入眠させよう
赤ちゃんをゆらゆら揺らすと泣き止むというのはママパパなら誰もがやったことがあるのではないでしょうか。実はゆらゆら揺らすというのは「鎮静反射」という強力な神経反射の働きによって泣き止んでいることが解明されています。この「鎮静反射」に着目したハーヴェイ・カープさんの提唱した赤ちゃんを穏やかな気持ちにさせる五つのスイッチが以下になります。
- 「おくるみ」できっちりとくるむ
- 「横向き/うつぶせ」にする(安全上、腕に抱っこしている時のみ)
- 「シーッ」と声で低く強いホワイトノイズを出す
- 「ゆらゆら」とリズミカルな動きをする
- 「おしゃぶり」をする
引用元:わが子がぐっすり眠れる魔法のスイッチ(著者:ハーヴェイ・カープ)P55を元に筆者修正
ちなみに、おくるみは眠りの妨げとなるモロー反射(びくっと両手を広げる動き)を防ぐ効果もあり、セントルイス・ワシントン大学の睡眠研究室の実験によって、睡眠中の赤ちゃんの突然の動きや興奮が、おくるみをしていないときよりも90%も減少したことが知られています。
おくるみで包むのが面倒だったり、難しいなという人には、ファスナー式(スワドルアップ)やマジックテープ式(スワドルミー)の成型済みおくるみもあります。
おくるみの使用は寝かしつけに有効ですが、乳幼児突然死症候群のリスクを下げるためにも赤ちゃんが暑くなりすぎないようにする(室温を快適に保つ)ことや、寝返りをはじめたらおくるみから卒業することを考えたほうが良いと言われています。

赤ちゃんが気に入る寝かしつけ方が見つかると良いですね。もちろんママパパのオリジナルの寝かしつけ方でOKです。
眠っている途中で目を覚ましにくくさせよう
睡眠は、浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)が周期的にきていることが知られています。赤ちゃんは睡眠周期が短く、浅い眠り(レム睡眠)の比率が高いことから目を覚ましやすい状態にあります。
- 睡眠周期が短い(大人は約90分周期、赤ちゃんは約60分周期)
- 浅い眠りの比率が高い(大人は約15%、赤ちゃんは約50%)
寝言 (泣き声)は2〜3分様子をみよう
浅い眠り(レム睡眠)の時には、赤ちゃんは寝言(泣き声)を出したり、寝返り(体をびくっとさせたり、手足をバタバタ)させたりします。
そのため、夜中に赤ちゃんが泣いた時にママパパが慌てて対応すると、寝言(泣き声)を出しながらも再び眠ろうとしている赤ちゃんの目を覚まさせてしまうことになりかねません。
寝言(泣き声)を出している時は2〜3分程度様子をみて、赤ちゃんが自力で再び眠りにつけることを期待しましょう。

赤ちゃんが眠っている最中に急に泣き出したり、バタバタしても、ママパパは抱っこしたい気持ちをぐっと抑えて様子を見守ろう
寝かしつけた状態をキープしよう
ママパパに寝かしつけてもらって、眠りにおちる赤ちゃんはとても安心しています。そして、眠るためにはママパパの寝かしつけの安心が欲しいと強く願うようになります。
そのため浅い睡眠(レム睡眠)で目が覚めそうな時、赤ちゃんは寝かしつけられたときと違う状況に置かれていることに気づくと不安になって泣き出してしまいます。
入眠のクセがある赤ちゃんは自分の力で眠りに戻れないために泣いて寝かしつけてもらおうとしてしまいます。
すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本(著者:ねんねママ(和氣春花))p78
そのため、寝かしつけの方法はできるだけ簡単で、夜に泣いた時に同じように対応できるような方法がおすすめです。

赤ちゃんを寝かしつける方法は色々あるけど、「やりすぎない」ことが大切なんだね
また、実施するには少し勇気がいる方法として、夜中に赤ちゃんが目を覚ました時、一人で眠りに戻っていける子に育てるために、起こしてまた寝かすという方法があります。
赤ちゃんが腕のなかで眠ってしまったら、ベビーベッドに下ろしたあと、オムツを替えるとか、少しくすぐるとか、おでこを冷たい手で触るなどして、ほんのちょっとだけ赤ちゃんの目をさましてあげてください。赤ちゃんは二、三秒くらい目を開けるか、小さな声を上げてあなたの手を払いのけようとしたあと、自分で眠りに戻っていくはずです。
わが子がぐっすり眠れる魔法のスイッチ(著者:ハーヴェイ・カープ)P134

1人で眠りに戻っていけるように「起こしてまた寝かす」を実践しています。
深い眠り(ノンレム睡眠)落ちた後は、赤ちゃんの睡眠圧が高まっているせいか、自分で眠りに戻ってくれる気がします。ただ、逆に目を覚まさないこともあって諦めることも・・・
まとめ
本記事では生後0ヶ月のおねんねに役立つ情報をまとめました。正しい知識・ノウハウを活用して赤ちゃんがスヤスヤ眠りについて、ママパパの自由な時間が増えることを願っています。
- 眠りやすい環境を整えよう
- 夜は真っ暗にして、体内時計を整えよう
- 夜はホワイトノイズを使ってほどほどに静かにする
- 温度湿度は大人が快適(少し涼しいくらい)に調整する
- 赤ちゃんの不快を取り除こう
- 赤ちゃんが起き続けられる時間は約40分なので、積極的に寝かしつけをしよう
- お昼寝しすぎている場合は、お昼寝時間を減らして夜の睡眠を増やそう
- 赤ちゃん自身に不快な要素がある場合は、原因を対処しよう
- 寝かしつけテクニックを知ろう
- 5つのスイッチを使って穏やかな気持ちにして入眠させよう
- 寝かしつけた状態をキープするために、簡単な寝かしつけか起こして寝かそう
もちろん正しい知識・ノウハウを身につけてもなかなか上手くいかないのも赤ちゃんの寝かしつけです。赤ちゃんの個性もありますので、どこまで知識・ノウハウを活用して寝かしつけるかはママパパの感性におまかせします!

少しでもママパパに役立つ情報が提供できれば嬉しいです。
これからもよろしくお願いします。
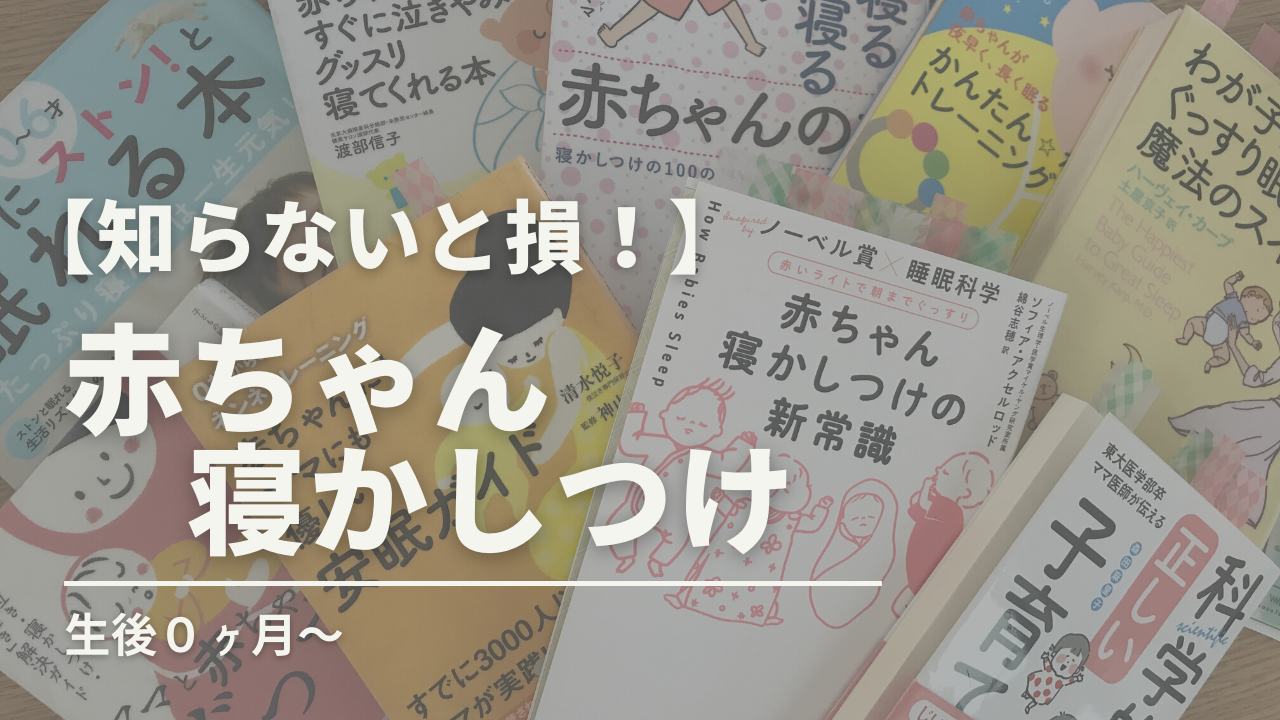

コメント